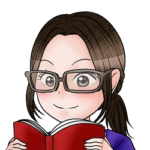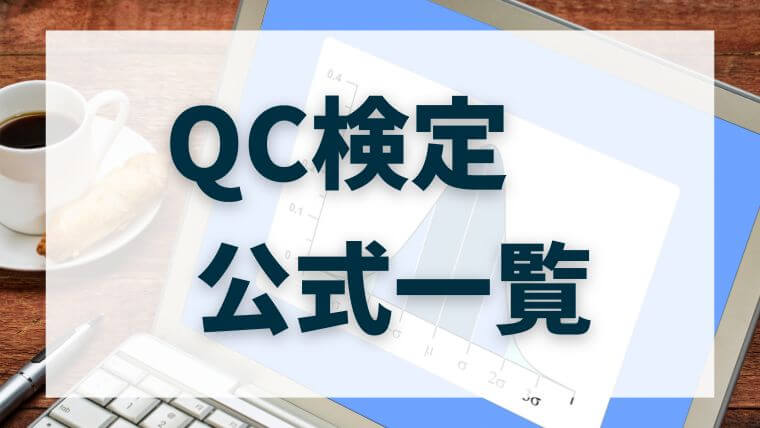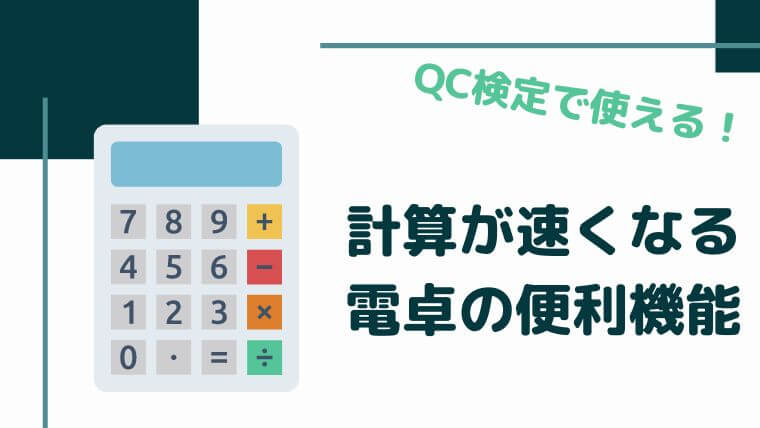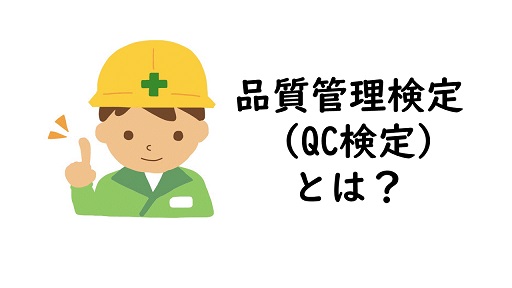QC検定2級 一発合格した勉強方法を解説。勉強時間とおすすめ教材
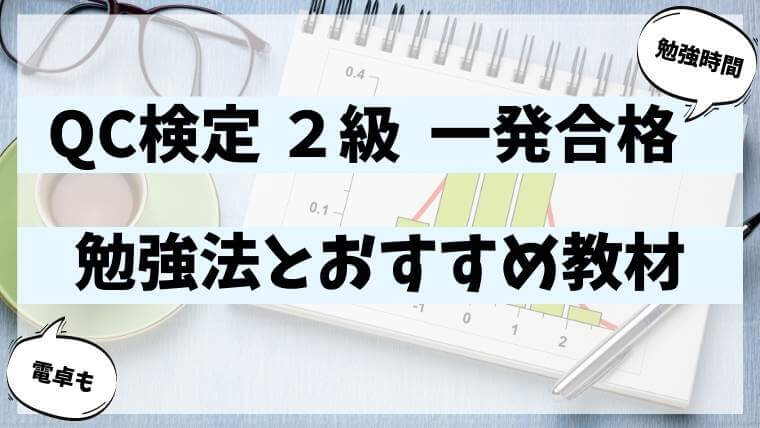

QC検定ってどんな勉強すればいいのかな?どのくらい勉強が必要?

独学で4ヶ月(合計70時間)で合格しました!
私は、製造業の会社に入ってから、品質管理検定(QC検定)を受験しました。
3級は持っておらず、いきなり2級から受験して、一発合格。
勉強記録によると、勉強期間は約4か月、合計時間は約70時間でした。
とはいえ、特別な勉強法やセミナーなどと受講したわけではありません。
テキストと過去問、問題集を使った独学のみでしたが、手法・実践どちらも、合格基準点を10点ほど上回る点数をとれました。
この記事では、実際に私が勉強した経験から、QC検定を独学で合格するための勉強法を解説していきます。
こんな方におすすめ
- これからQC検定を受けようと考えている
- QC検定 2級に合格する勉強法が知りたい
過去問は12月末に最新刊が出ます。購入する際は最新であることを必ず確認しましょう。
品質管理検定(QC検定)って何?という方はこちらをご覧ください。
QC検定2級 勉強の進め方
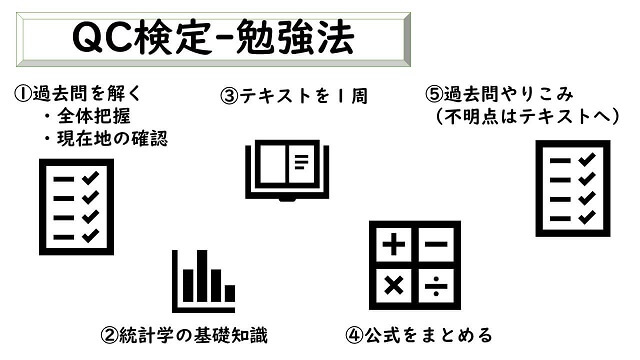
基本的な勉強の流れは以下のようになります。
QC検定2級 独学で合格する勉強法
- QC検定の過去問を時間を測って解く(現在のレベル確認)
- 統計学の概要を知る
- テキストを一周する
- 公式をまとめる
- 過去問を解き、理解が不足している部分はテキストに戻る
テキスト → 過去問へと進めるこの方法は、QC検定に限らず他の資格試験にも応用できる、王道のやり方です。
両方やるのは、面倒に思われるかもしれませんが、要は、急がば回れ
テキストだけでは実際の出題の形式や傾向がわからず、過去問だけでは網羅性が低いです。
テキストと過去問は必ずセットで取り組みましょう。

なるべく一回受験で終わらせるように、ちゃんと時間を作りましょう
①過去問を時間を測って解く(現在のレベル確認)
まずは過去問を1回分だけ解いて今の実力を確認してみましょう。
公式版の過去問は6回分入っています。ここはレベル確認なので、過去問集の中で、一番古い問題を使うのがおすすめ。
計算が多い手法はチンプンカンプンかもしれませんが、文章問題の実践編は意外と取れるかもしれません。
(ちなみに、私は手法は3割切ってました)
ここでは、採点はしますが、解説を読んで復習するのは後にしましょう。(⑤の段階まで)
あくまで、試験概要と自分の実力の把握が目的です。
②統計学の概要を知る
QC検定の2級の手法(計算)問題は、ほぼ統計です。
ですので、統計学の基礎を最初に頭にいれてからスタートしたほうが、理解がしやすくスムーズです。
統計は部分的にかいつまんで読んでも理解しづらいです。
簡単な統計学の本を通して読み、全体像をつかみましょう。

私は、この統計学入門という本を使って、問題を解きながら進めました
読むだけでなく、練習問題も解きながらすすめてください。
実際に問題を解くことで、”わかったつもり”になってしまうことを防げます。
しかし、まったく統計になじみがない、文章ばかりはちょっと、という方はマンガをおすすめします。

まんがなので読みやすく、とっつきやすいです。
お金をかけたくない場合、統計WEBさんのページは情報量が多いので参考になります。
③QC検定2級のテキストをざっくり一周する
はっきりとは理解できないところがあるかもしれませんが、まずは一周して全体を把握します。どのような分野の問題が出題されるのかを確認しましょう。
私は、問題もついているこちらのテキストを使用しました。
次に、もう一度頭から読みつつ、練習問題と巻末問題を解いていきます。
わからない場合は、もう一度テキスト部分に戻って復習しましょう。
文章を読んだだけではよくわからなかった部分も、問題を解くことによって理解できることも少なくありません。

最近出版されたユーキャンのテキストは図解が多く、わかりやすいです
ただし、30日といわずもう少し余裕をもって勉強を開始しましょう
④QC検定2級の公式をまとめる
過去問に進む前に、一度公式をまとめておきましょう
私が使ったテキストでは、残念ながらまとめページはありませんでした。
改めて書き出して整理してみると、それぞれに関連性や類似性があることがわかります。

私は下の画像のようにエクセルにまとめて、空欄で印刷し、何回も書いて覚えました。
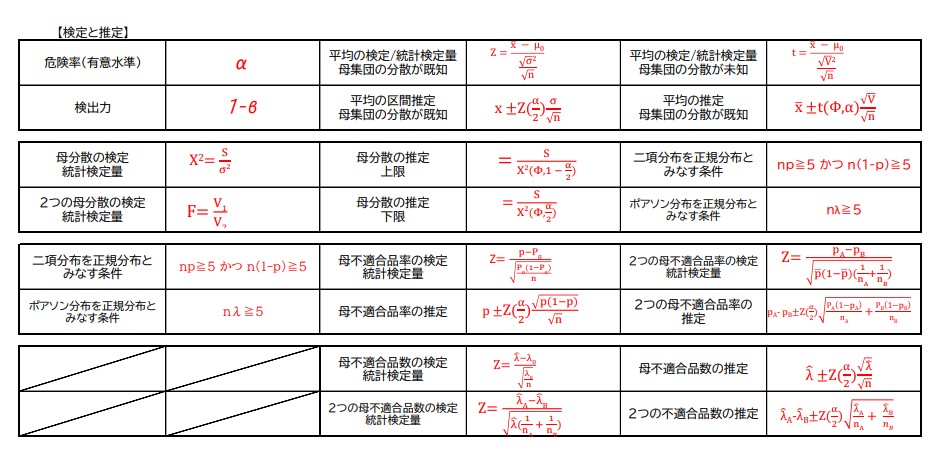
こちらのページに自作でまとめた公式一覧表がありますので、よろしければご活用ください。
2級の場合は公式を知らないと解けない問題も多々ありますし、逆に公式さえ知っていれば、与えられた値から逆算して解くようなことも可能です。

公式は繰り返してしっかり覚えましょう。
⑤QC検定2級の過去問を解く
最後に、過去問です。
資格試験を受ける場合には、過去問を解くことは必須の作業です。
最初に解いた1回分も含め、過去6回分をやりこみましょう。
全ての過去問を一気に解くのではなく
- 1回分解いてわからなかったところを復習
- その問題がしっかり解けるようになるまで復習
- 次の過去問に進む
と順番にやっていきましょう。
過去問の解説が分かりにくい場合は、これもまたテキストに戻り確認してください。
テキストに載っていない場合は、上記の統計学などの本を参考にします。

過去問をやりこんでさらに練習したい場合は、追加で問題集などに取り組みましょう。
電卓はQC検定の勉強に取り掛かる前に準備する
QC検定に使う電卓は、何でもいいわけではありません。
これから買う方も、お手持ちのものを使う方も、直前になって慌てないように、必ず以下のポイントをチェックしてください。
- 関数電卓は持ち込み禁止
- ルートキーがついているもの(ルートがないと平方計算ができないので詰みます)
- グランドトータルキー(GT)、メモリーキー(M+、M-、MR)がついている
- 大きめで打ちやすい
- 簿記なども意識している方は10桁より12桁
QC検定におすすめの電卓
メーカーによってキー配置が異なります。
試験に持ち込む電卓は早めに準備して、勉強中から使って慣れておきましょう
電卓での便利な計算方法も知らないと損
手法問題は電卓計算が多いため、いちいち1つ1つキーを押したり、計算結果をメモっていたりしたら時間もかかるし、ミスも多くなります。
電卓の基本的な計算方法をマスターすることは、合格への近道
以下の記事に最低限知っておきたい3つの機能を載せていますので、ご参照ください
QC検定2級の勉強するなら現状を確認しよう
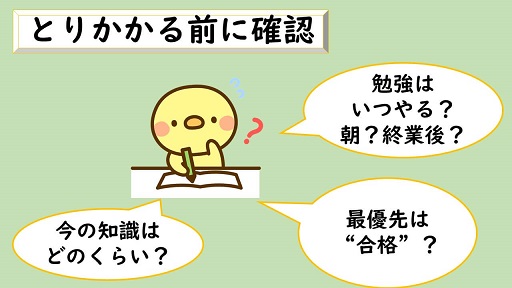
まず最初に確認すべきなのは、こちら
- 受験の目的
- 勉強にあてる時間
- あなたの現在地
順番に説明していきます。
あなたがQC検定を受験する目的
要は、試験に受かればいいのか、業務で使う予定なのか。
多くの人は知識を得ることよりも、合格して資格を取ることが最優先だと思います。(私もそうでした)
その場合に、大事なこと。それは、完璧を目指さないことです。
品質管理・統計は奥が深いので、完全に理解してから次に進みたいなどと完璧を求めていると、勉強時間が足りなくなったり、挫折の元になります。
資格試験は一定の基準に達すれば合格。
合格だけを目指すなら、7割を取ればいいんです。
(これは他の試験にも当てはまりますね。)

目指すは100点でなく、7割!
QC検定のための勉強時間を確保する
あなたは、いつ勉強しますか?
どのくらい時間がとれますか?
2級は時間があるときにだけ勉強するやり方では、確実に合格することは難しいです。
特に、手法(計算問題)は繰り返し解いて定着させる必要があるので、きまった時間をコンスタントに確保しましょう。

毎日勉強する時間&場所を決めてコツコツ!
現在の自分のレベルを認識する
ゴールと同時に重要なのが、あなたの現在地です。
次のような場合は有利であり、イチから始めるよりも勉強時間は短くなります。
- 統計の知識がある(特に手法編に有利)
- 品質にかかわる仕事をしている(特に実践編に有利)
- すでに3級を取得している
逆に全く、経験も知識もない場合は、基礎からやっていく必要があります。
現在値がわからない方は、過去問を時間を測って解いてみてください。
さっぱりわからないか、なんとなくわかるか、どのくらい点数がとれるか自分の手ごたえを確認してみましょう。

合格する試験勉強=今の点数と合格基準とのギャップを埋める
まとめ:QC検定2級は独学でも合格できる!
品質管理検定は、7割取れれば合格する試験です。
QC検定 2級に独学で合格する勉強法
- 過去問を解いてみる
- 統計の知識を知る
- テキストをざっくり1周
- 公式をまとめる
- 過去問を解く。不明点はテキスト

がんばってください!
申し込みはこちらから QC検定の公式サイト